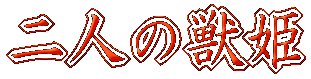
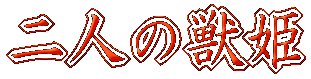
プロローグ〜
私の前には、二人の少女が横たわっている。
暖炉の前、暖かい炎の前で。
ソファーの上ではなく絨毯の上に。
眠るように静かに。
二人、寄り添うように・・・。
二人の獣姫。
私は、この美しい獣たちに魅せられてしまった。
扉の外で、本来のこの屋敷の持ち主である男が、怒鳴り声を上げている。
ドスドスと下品な足音が、この部屋に近づいている音が聞こえる。
少女たちは、スッと音も無く立ち上がる。
そのまま扉に向かい立ち尽くす。
扉が開くと同時に、男が踏み込んできた。
この地方の領主であり、この屋敷の主であった男だ。
「オイ、どういうことだ?何故誰も出迎えない?カラバは?ディアーナは何処だ?」
少女は手にした剣を一閃させる。
まるで初めから取り外しがきく玩具の様に、男の首がポトリと落ちる。
「アナタ・・・うるさいの。」
どうやら彼を殺したのは、ただそれだけの理由だったらしい。
「まだ、他にもウルサイやつらがいるみたいだから…片付けてくる。それまでにこれ始末しておいてね。この部屋に、これは、要らないわ。」
そう言ってかつてこの屋敷の主であったものを指差し、この部屋を後にした。
「はい。」
すでに居なくなった彼女たちの残像に向けて、私は恭しく頭を下げた。
これは、この屋敷が二人の少女のものになった時の話だ。
あの、まだ雪が降り始めたばかりの…冬の初めの物語。
私が…美しい一対の獣姫に心を奪われた時の……。
第1章 二人の少女
滝のように降り続ける激しい雨の中を、みすぼらしい姿の二人の少女が走っていた。
ボロボロの衣服は、雨を吸って更にボロボロに見えて、哀れさを増している。
彼女たちの腕の中には、さっきまで農家で飼われていた鶏がいた。
二人は、ある農家からその鶏を奪ってきたのだ。
食べる為に。
二人は、住処にしている洞窟にやっとたどり着いた。
そしてすぐに彼女たちは、拾って貯めてある木切れを使って火をおこした。
濡れた服を脱ぎ、絞って洞窟内に張られたロープにその服をかける。
満足に食べられず、栄養が足りない為、彼女たちの身体は、ガリガリに痩せ細っている。
その光景はあまりにも痛々しい。
彼女たちは、体を拭くタオルも、着替える為の服も持っていない為、体を犬のようにブルっと振って水気を僅かでも飛ばすと、裸のまま今度は、鶏の解体を始めた。
「キリエ。これで今日は、久しぶりにご飯、食べられるね」
体の微妙に大きな方の少女が、もう一人の方の少女にそう語りかけた。
「そうだね、ユーイ」
やや小柄な方の少女はそう、返事をした。
喋りながらも二人の手は、休むことなく鶏の毛を毟っていた。
「キリエ。この羽は、後でお布団の中に入れようね。そしたら、少しは暖かくなるよ」
「うん、それ良い考えだね。毎日寒いもんね」
布団といっても、二人が言っている布団とは、ただのボロキレだった。
誰かが捨てたボロキレを紐で二枚合わせにして、その中に普段は、落ち葉や紙くずを拾ってきて暖かさを増す努力をしていた。
その中にこの羽毛を入れれば、暖かさが少しは増すかもしれない。
連日寒さが増していくこの辺りでは、少しでも暖かくしておかなければ凍死してしまうかもしれない。
羽を毟り終わった二人は、ナイフを使って捌き始めた。
拾ってきたナイフだが、一本しかないので大事に大事に研ぎながら使っているナイフなので切れ味は悪くない。
ある程度の大きさに切り分け、焚き火の為の囲いを作っている石の上に肉をのせる。
その上に置いておけばいい感じに火が通って肉を食べやすくしてくれるのだ。
炎によってすでに熱くなっていた石は、鶏肉を焦がし香ばしく食欲をそそる匂いを発し始めた。
「いい匂い・・・」
キリエは、その匂いを思いっきり吸い込んだ。
これは、二人にとって、3日ぶりのまともな食事だった。
3日間、二人は魚も肉も手に入らず、山の中で虫や草をとって来て飢えをしのいでいた。
あまり奇妙なものを食べるとお腹を壊し、大変な目に合うこともしばしばだが、食べなければ生きる事が出来ない。
生きる意味も二人には分からないが、ただ死にたくは無かった。
気がつけば二人は、今みたいな生活をしていた。
普通に喋ることも出来たし、お互いが姉妹だということも認識できた。
少なくとも、自分たちが人間であって獣ではないということは、分かっていた。
でも、自分たちが何故、こんな暮らしをしなければならなくなったのかは分からないし、以前どんな暮らしをしていたかも知らなかった。
そのことを知りたくないかといえば、そんなことも無かったが、それ以上に生きる事が重要だと考えていた。
人は食べなければ確実に死ぬのだから。
このあたりに移り住んですでに2週間が過ぎた。
あまり同じところに長くいると、そのあたりの住人に目をつけられる。
盗みもやりにくくなる。
だから彼女たちは、気まぐれに住処を替え、さらに遠くへ移動し、なるべく同じ場所には居ない様にしていた。
だからこのあたりも、それほど長く居ることは無いだろう。
ただ、寒くなって冬が近づいているようだったので、あまり遠くまで行けない。
確実に寒さを凌げる所を見つけないと、雪が降り始めれば、凍え死ぬ事になるかもしれなかった。
ただ死なないだけの、生き続けていくだけの生でありながら、挫けず、頑張れるのは、一人ではなかったからだ。
半身ともいえる、姉妹。
気が付けば、お互いがすぐ側にいた。
アレはいったい、いつの頃だろうか?
二人には、その頃からの記憶しか無く、それ以前の記憶は無かった。
どこかで、自分を逃がす人がいた様な気がするけれど、それもあやふやな記憶でしかない。
キリエは、ユーイがいれば良かったし、ユーイは、キリエがいれば良かった。
あちこちで目にする、暖かい家も、美味しそうな食事も、家族という不思議な関係も自分たちには縁が無かったが
それを知らないのだから不満には思わなかった。
知らないという事も分からず、二人は今まで生きてきたのだ。
思いやるという言葉も知らずに、お互いを思いやり、愛するという言葉も知らずにお互いを愛した。
寒さが身にしみれば、抱き合って眠り、食べ物が少なければお互いに半分づつ食べ、無ければ一緒に探して歩き
怪我をすれば、どちらかが傷に効く草を探し出して手当てをし、ずっとずっと二人で協力しながら生きてきたのだ。
二人で一人の関係。
どちらかが欠ける事なんて、お互い考えられなかった。
「残りは、明日も食べようね。一日で全部食べちゃったら、明日また何も食べられないかもしれないもん。」
そうユーイが言って、焼いた肉を紐で吊るし、天井に掛けた。
「そうだね。また何日も食べられないかもしれないし、また盗ってくるにしても運が悪かったらアタシ達が捕まっちゃうかもしれないし。」
「そうそう。今度盗るとしたら違う家からだね。同じところじゃ警戒されてるよ、きっと!」
食事が終わると二人は、毟った羽毛をボロギレ布団に入れた。
心なしか膨らんだ気がする布団は、二人の身体を優しく包んでくれた。
布団の中でお互い抱き合うように身を寄せ合い、暖めあう。
冷たい雨に塗れた身体は、炎によって暖められていたが、それでも今はもう、かなり寒い季節。
少しでも、暖気を逃がさないようにピッタリと密着する。
燃え残った木切れがパチパチと言う音を立てて燃えている。
その炎の作りだす明かりがお互いの顔を照らし出している。
お互いの頬を手の平でそっと包む。
「ふふふ。」
二人は、どちらからともなく微笑んだ。
多分、同時に。そのくらい心は、通じ合っている。
「美味しかったね、鳥。」
キリエが、そう言った。
ユーイは、うん美味しかったね、と答えた。
「それはともかく、雪が降り始める前に、もっとちゃんとした所を見つけないと、アタシ達、凍え死んじゃうよ。」
キリエは、ユーイのその言葉を聞いて真剣な眼差しで見つめ返し、彼女の背中に手を回し、抱きしめた。
「そうだね。それに去年みたいにユーイが病気になったりしたら大変だもんね。今度はアタシの番かも知れないし。」
ユーイは去年の冬、風邪を引いていた。
何日も何日も治らず、キリエは、ユーイがこのまま死んでしまうのではないかと思った。
寒い、寒いというユーイをキリエは、自分の身体を使って温め、雪の中栄養の有りそうな物を探し回った。
ユーイが治ったのは、奇跡のような気がした。
「病気は、怖いね。薬があれば、すぐに治っちゃうって話だけど、アタシ達には手に入らないもんね…。」
「うん、不公平だね。何でアタシ達には、何にも無いんだろう。お金も住む所も食べる物も・・・なんで無いんだろう?」
「そうだね、いっぱい無いね。でも何も無いってのは違うよ。キリエには、アタシがいるし、アタシにはキリエがいるよ。」
キリエは、ユーイのその言葉を聞いて目頭が熱くなった。
「ユーイィ・・・。そうだね。アタシ、ユーイがいるから頑張れるよ。」
ユーイの目にも涙が滲んだ。
「アタシだって、キリエがいれば、頑張って生きていけるよ。ずっと一緒だよ。」
「うん!」
二人は、なんとなく幸せな気分になって、心の暖かさを感じながらその日は、静かに眠りについた。
二人が翌朝、寒さで目を覚ました時、洞窟の外には、白い雪が降っていた。
今年は去年より、初雪が降るのが早い。
雪は、地面に落ちると、すぐに解けて消えていった。
この分なら積らないだろうと、二人は安堵した。
しかし、急いでもっと暖かい場所を探すか、この洞窟で冬を越せるように改造して食料を運びこまなければいけない。
二人には、時間が無かった。
つづく・・・